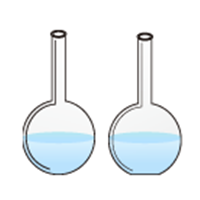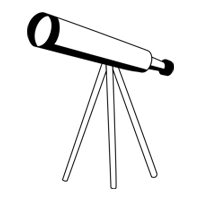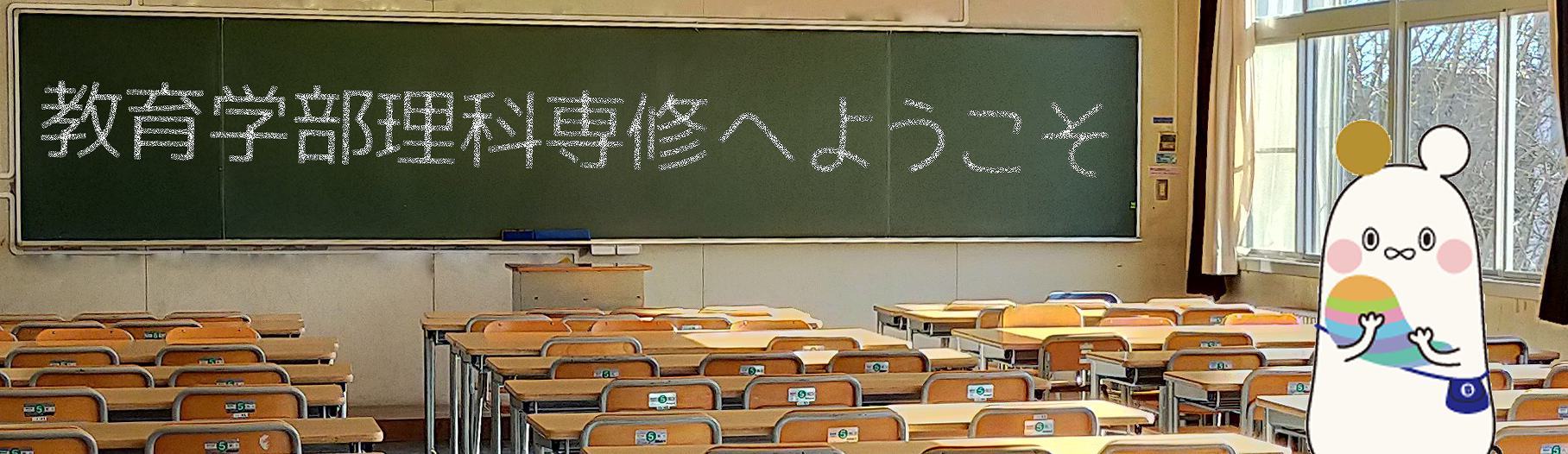
ようこそ理科専修へ
理科専修に入学した皆さんのほとんどは、中学校や高等学校の理科の教員、あるいは理科を得意とする小学校の教員を目指しているものと思います。
では、教員となるにあたって、理科の内容についてどの程度深い知識が必要だと思いますか?世間では、小学校なら小学校で教える内容を、中学校なら中学校で教える内容を理解していれば十分教えられる、という誤解が少なくありません。実際には高校で習う内容が最低限必要なレベルで、まともな教師になろうと思えば大学で習うような知識も必ず必要になります。
いまの日本の高校カリキュラムでは、残念ながら物理・化学・生物・地学のすべてを習うことはまずできませんので、他の教科と異なり、みなさんは始めから不条理な立場に立たされていますが、早いうちに高校の理科の内容はマスターしておいてください。
なぜそれだけの深い知識が必要なのでしょうか。
小さい子どもの会話を聞くとわかりますが、子どもは子どもなりにわずかな断片的な知識を組み立てて頭の中に世界を構築しようとします。
そのため、大人から見るとつい笑ってしまうような間違いもたくさんします。
しかし、大人だって似たようなものです。知識の量が増えたのであまり気付かれないだけなのです。
皆さんが教壇に立ったとき、子どもたちからやって来る質問は、教科書の範囲に納まるとは限りません。
ニュースや科学番組で知った最先端のことについての質問かもしれません。
そんなとき、断片的な知識から間違った回答をする教師は少なくありません。結果的に子どもに嘘を教えてしまうこともあれば、煙に巻いてごまかすこともあります。
しかしこれでは理科への興味は育ちません。こういうところで教師の力量が問われるのです。
教師としての力量を一本の木にたとえるならば、高校までの学習は根のようなものです。大学の授業は幹を作ります。
しっかりした根がなければ、幹も細いものにしかなりません。
幸いなことに、根はいまからでも生やせます。
自分でしっかり学習して、しっかりした根を作ってください。
さて大学の授業で作れるのは幹までです。では枝や葉や花はどうすればいいでしょうか。
これはみなさんが自分で生やすしかありません。
ここが高校までの学習と決定的に異なる点です。
大学の授業をベースに、皆さん自身が自ら学び、花を咲かせ、豊かな実りを獲得してください。
教師になったら自分が教える立場になりますので、あとは自ら学ぶしかありません。
大学卒業後、40年にわたって教え続ける
ためには、進化しつづける理科の内容を不断に学ぶ必要があります。
「自ら学ぶ」のはそう簡単なことではありません。
そのための基礎的な力を大学では学ぶことになります。
なお、文部科学省の方針によって、卒業に必要な単位数や、理科の免許取得に必要な単位数が定められていますが、これも教師になるにあたっての最低限でしかありません。
良い教師になるには到底足りないのです。
「選択」となっている授業も積極的に受講しましょう。
大学では、理科の内容だけではなく、指導法についても学びます。
学ぶ立場から教える立場になるためには必要な知識です。
それ以外にも、教育に関する幅広い授業があります。
これらをマスターして、自分の考える、自分なりの「良い教師」像を構築し、一歩一歩近付いていきましょう。
大学4年間はあっという間に過ぎ去っていきます。
時間を有効に使って、有意義な理科専修での大学生活を送ってください。
私たち教員はできる限りのサポートをします。
授業外でも積極的に質問をしに研究室まで来てくれればと願っています。
理科専修主任
長島 雅裕
化学研究室
生物学研究室
地学研究室
理科教育学研究室
教 授
教 授
教 授
准教授
船山 智代
平山 順
山縣 朋彦
山野井 貴浩