2年生の春学期には、家庭専修必修科目である、「基礎調理実習」が行われています。「家庭科の授業で調理実習を行う」ということを前提に学生たちは白衣に身を包み班ごとに調理しています。調理後はレポートを書くという課題が待っていますが、その前にお楽しみの試食タイム。毎回美味しそうな香りが1階の調理室から漂ってきます。(助手G)
5月23日、家庭経済学の授業にて、関東財務局の方による2週連続講座の第2回「金融リテラシー講座~将来 金融経済教育を担う皆様へ~」が行われました。
今回は、小学生向け金融教育の実践例として紹介された「キッズマネー講座」をベースに、「お小遣いすごろくゲーム」の体験を通じて、子どもたちにとっての“お金の学び”を疑似体験しました。
お金の役割や使い方、電子マネーと現金の違い、「必要なもの」と「ほしいもの」を分けて考える視点など、ゲーム形式ながらも本質的なテーマに触れる内容でした。
楽しさの中にもしっかりとした学びがあり、教員として子どもたちに何をどう伝えていくかを考える貴重な時間となりました。(助手H)
5月16日、家庭経済学の授業にて、財務省関東財務局の方による「金融リテラシー講座」が行われました。
この日の講義にはテレビ埼玉の取材も入り、学生がインタビューを受ける場面もありました。
(文教大学のHPにも掲載されています。https://www.youtube.com/watch?v=PhI8WnX56qg (テレ玉NEWSチャンネル))
講義では、ボリュームのある資料をもとに、金融や家計管理に関する基本的な知識をはじめ、株式投資や投資信託などを学びました。
近年増加しているSNSを使った「著名人になりすました投資詐欺」などの具体的な事例も紹介され、日常生活に潜むリスクに対する注意喚起も行われました。
来週は、実際に小学生向け講座の際に使われている「お小遣いすごろくゲーム」を体験する予定です。子どもたちにとっての金融教育とはどのようなものかを、学生自身が体験を通して考える機会となるでしょう。
金融の知識を“自分ごと”として捉え、判断力を養っていく。その第一歩となるような時間でした。(助手H)

綿を植えて1か月が経過しました。本葉も出てきて順調に成長しています…?
梅雨の時期に入って、根腐れしないと良いのですが…
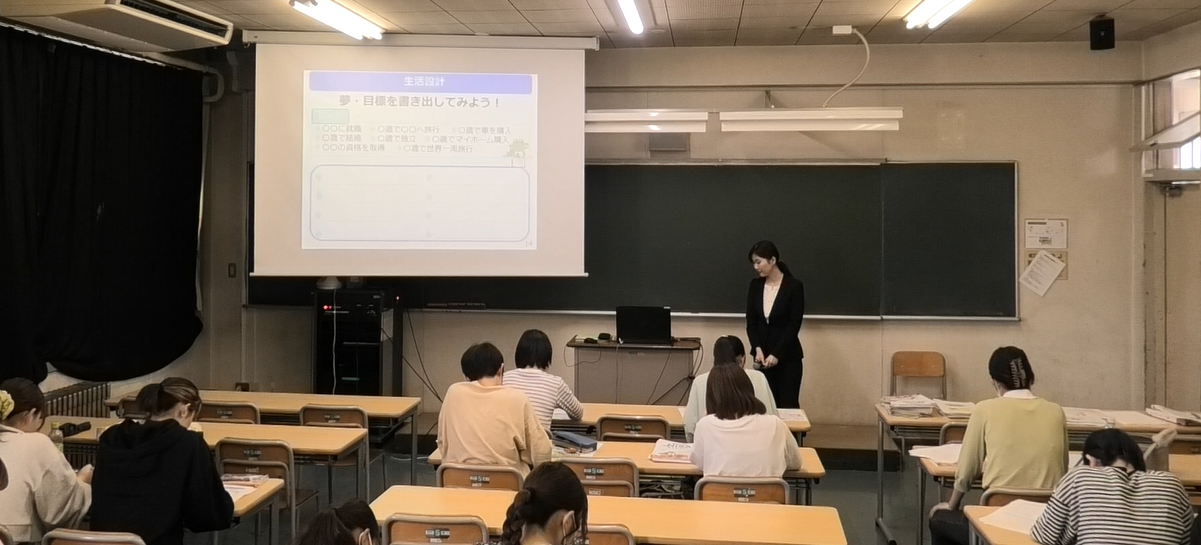
4月26日、家庭経済学の授業にて、関東財務局の方による講義が行われました。
人生100年時代と言われる現代において家庭科を教えるには、金融リテラシーも大事なことです。
学生自身が金融に関する知識を身に着けるとともに、どのように教えたらよいかということも考えつつの学び多き時間となったのではないでしょうか。(助手G)